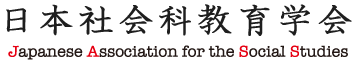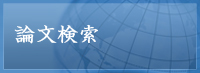機関誌目次
現在、検索できるのは「タイトル」「著者名」のみです。以下の手順で検索可能です。
- 右上の検索窓に「タイトル」「著者名」に含まれるキーワードを入力する。
- 「サイト内を検索」ボタンを押してから、検索を実行する。
No.1~10 | No.11~20 | No.21~30 | No.31~40 | No.41~50 | No.51~60 | No.61~70 | No.71~80 |
No.81~90 | No.91~100 | No.101~110 | No.111~120 | No.121~130 | No.131~140 | No.141~145
第91号-100号
第91号(2004年)
| 〈特集テーマ:社会科と新学習指導要領〉 | |
| 「国家・社会の形成者」を育成する中学校社会科授業の開発 ―公民単元「選挙制度から民主主義社会のあり方を考える」― |
池野 範男 渡部 竜也 竹中 伸夫 |
| 単元「イブン・バットゥータが旅した14世紀の世界」の開発 ―新学習指導要領世界史Aにおける「ユーラシアの交流圏」の教材化― |
田尻 信壹 |
| 歴史的思考力の基礎概念としての地理的見方・考え方 ―世界史前近代の認識形成を中心に― |
戸井田克己 |
| 〈研究ノート〉 | |
| 社会科教育における文書館の意義 | 永井 博 |
| 〈研究の広場〉 | |
| 日本社会科教育学会国際シンポジウム報告 | 国際交流推進委員会 |
| 〈図書紹介〉 | |
| 2003年度日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |
第92号(2004年)
| I 特集テーマ:社会科教育と新しい時代の"公共性" | |
| ≪シンポジウム≫ | |
| 社会科教育における公民、市民概念の再検討と「公共民」の提唱 | 山口 幸男 |
| 公共性問題の射程 -社会科教育の批判理論- | 池野 範男 |
| "新しい公共性"と社会科の改善 | 工藤 文三 |
| システム論的「私・共・公」三元論による社会系教科教育の構想 -秋田大学における実践を中心にして- |
井門 正美 |
| 公共圏概念の導入による社会科の改善 | 内山 隆 |
| 社会科における"公共性"とその教育についての若干の考察 -「法教育」における議論を手がかりとして- |
江口 勇治 |
| ≪論 考≫ | |
| 「新しい公共性」論と公教育 | 林 量俶 |
| 生命「倫理」教育と/の公共性 | 大谷 いづみ |
| 「サイバースペース」における「公共性」と社会科教育 | 佐藤 公 |
| ≪研究動向≫ | |
| 社会科における公共性の扱いと授業構成論の類型 | 桑原 敏典 |
| II 研究調査 | |
| 理論研究: 社会科教育における理論研究の動向 -2003年度の研究成果をもとに- |
小野 智一 |
| 実践研究: 「現場」からみた社会科教育実践の動向とその課題 -2003年の実践研究をふりかえって- |
須賀 忠芳 |
| 海外研究: 現代中国の教育課程改革と歴史教育の革新 |
森茂 岳雄 桐谷 正信 森田 真樹 |
第93号(2004年)
| 《研究論文》 | |
| 戦前の師範学校における公民教育 -昭和10年代の師範学校における「公民科」及び「国民科修身公民」の検討を通して- |
木村 勝彦 |
| 《研究ノート》 | |
| いじめ裁判判決文を活用した授業に関する研究 -法的理解や法的判断力との関係を中心にして- |
新福 悦郎 |
| 《研究の広場》 | |
| 法教育の今後の展開 -法務省「法教育研究会」における議論から- |
大杉 昭英 |
| 「教科等の構成と開発に関する調査研究」における社会科、生活科に関する研究 | 工藤 文三 谷田部 玲生 二井 正浩 |
| 《書評》 | |
| 三浦軍三著『米国の公民育成研究』 | 中村 哲 |
| 坂井俊樹著『現代韓国における歴史教育の成立と葛藤』 | 二谷 貞夫 |
| 久野弘幸著『ヨーロッパ教育 歴史と展望』 | 大友 秀明 |
| 桑原敏典著『中等公民的教科目内容編成の研究-社会科公民の理念と方法-』 | 江口 勇治 |
| 草原和博著『地理教育内容編成論研究-社会科地理の成立根拠-』 | 西脇 保幸 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第94号(2005年)
| 《研究論文》 | |
| 学際的サービス・ラーニング・プログラムにおける社会科の役割 -'CityYouth'の分析を通して- |
唐木 清志 |
| 世界史教育における「人種」概念の再考 -構築主義の視点から- |
高橋 健司 |
| 《研究の広場》 | |
| 平成16年度日本教育大学協会社会科部門関東地区研究集会の報告 | 野口 剛 |
| 《書評》 | |
| 二谷貞夫編『21世紀の歴史認識と国際理解』 | 田渕 五十生 |
| 市川博編著『問題解決学習がめざす授業と評価』 | 溜池 善裕 |
| 《図書紹介》 | |
| 2004年度日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |
第95号(2005年)
| I 特集 グローバル化する地域・国家・世界 -「大学・地域連携」の中で- | |
| 《シンポジウム》 | |
| グローバル化する地域・国家・世界と教師 -「大学・地域連携」の中で- |
魚住 忠久 |
| グローバル化する地域・国家・世界における大学と地域の連携を通じた 学校の教育力向上プラン -公州大学校師範大学の「教育現場研究フォーラム」の実践と計画を中心に- |
李 明熙 |
| グローバル化する地域・国家・世界における 教員養成と課題としての「大学-地域連携」 |
森茂 岳雄 |
| PISA‐Schock und Schulreformen -Internationale Leistungsvergleichsstudien und ihre Folgen fur die Bildungslandschaft in Deutschland- |
Oliver MAYER |
| (抄訳) PISAショックと学校改革 -国際比較研究がドイツの教育に与えた影響- |
久野 弘幸 |
| 《論考》 | |
| グローバリゼーションと国家 | 磯崎 育男 |
| 対話における「聴く」の検討 -グローバル化した世界に創造的関係をもたらすもの- |
多田 孝志 |
| グローバルな市民育成と自己探究との統合 -「私」を見つめ直す開発教育教材の開発- |
木村 一子 |
| 《研究動向》 | |
| 社会科教育研究におけるグローバル教育についての考察 | 森田 真樹 |
| II 研究調査 | |
| 理論研究:社会科教育学における理論研究の動向 -2004年度の研究成果をもとに- |
吉村 功太郎 |
| 実践研究:社会科教育における実践研究の動向 -2004年度の研究成果を手がかりとして- |
鴛原 進 |
| 海外研究:ヨーロッパ機関(EU・CE)におけるヨーロッパ市民教育 | 久野 弘幸 |
第96号(2005年)
| 《研究論文》 | |
| 歴史叙述としての教科書 | 今野 日出晴 |
| 明治後期の「世界史」について | 鈴木 正弘 |
| 《研究ノート》 | |
| 明治期女子国語読本における「望ましい」公民的人間像 | 菅澤 康雄 |
| 地域ミニコミ誌づくりによるコミュニケーション能力の育成 -中学生の社会参加活動をとおして- |
中 善則 |
| 《研究の広場》 | |
| 金融教育をめぐる近年の動向について | 栗原 久 |
| ワシントン大学多文化教育センター "Democracy and Diversity: Principles and Concepts for Educating Citizens in a Global Age" (『民主主義と多様性:グローバル時代における市民の教育のための原理と概念』) プロジェクト報告 |
川﨑 誠司 |
| 《書評》 | |
| 梅野正信著 『社会科歴史教科書成立史 -占領期を中心に-』 | 田中 武雄 |
| 外池 智著 『昭和初期における郷土教育の施策と実践に関する研究 -『総合郷土研究」編纂の師範学校を事例として-』 |
影山 清四郎 |
| 《図書紹介》 | |
| 2005年度日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |
第97号(2006年)
| 《研究論文》 | |
| 1920年代植民地朝鮮の普通学校における「朝鮮事歴」教授 -郷土史概念を手がかりとして- |
國分 麻里 |
| 地域NPOネットワークとの連携による社会参加学習の意義と方法 -静岡大学教育学部附属浜松中学校の実践を通して- |
鈴木 正行 |
| 博物館の体験学習における児童の歴史意識の発達的変容 -小学校第三学年単元「昔のくらし」からの考察- |
松岡 葉月 |
| 《研究の広場》 | |
| 日本社会科教育学会 出版プロジェクト編『新時代を拓く社会化の挑戦』 の発刊にあたって |
影山 清四郎 |
| 法教育と裁判員制度教材ビデオ | 戸田 善治 |
| 「その日、教育の新たな可能性が集う」 -千大附属小教育フェアにおける法教育の取り組み- |
向井 浩二 戸田 善治 |
| 《書評》 | |
| 児玉康弘著『中等歴史教育内容開発研究-開かれた解釈学習-』 | 戸田 善治 |
| 大友秀明著『現代ドイツ政治・社会学習論-『事実教授」の展開過程の分析-』 | 池野 範男 |
| 井田仁康著『社会科教育と地域~基礎・基本の理論と実践~』 | 西脇 保幸 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第98号(2006年)
| I 特集 21世紀市民社会と社会科教育 | |
| 《シンポジウム》 | |
| 産業構造の変化と産業学習のあり方 -「起業教育」東北モデルの可能性- |
竹内 裕一 |
| 21世紀の世界と日本 -新世紀の5年を経て- |
長尾 龍一 |
| 社会事象の意味や構造を問いかけ学ぶ授業の構築をめざして -歴史学習の実践から考えること- |
平田 博嗣 |
| 「市民社会」よりも「人間の社会」を! | 小池 俊夫 |
| 《論考》 | |
| いかに法を普及させるか -模擬裁判の可能性- |
船山 泰範 |
| シチズン・リテラシーの開発 -出版及び社会科教育の役割- |
成田 喜一郎 |
| 21世紀市民社会における経済教育のあり方 | 山根 栄次 |
| II 研究調査 | |
| 理論研究:社会科教育学における理論研究の動向 -2005年の研究成果を手がかりとして- |
橋本 康弘 |
| 実践研究:社会系教科におけるメディアリテラシー教育 -メディアの活用とメディアリテラシーの育成- |
井門 正美 |
| 海外情報:トルコにおける社会科教育の動向と課題 -教科「社会科」を手がかりに- |
西脇 保幸 |
| 学会彙報 |
第99号(2006年)
| 《研究論文》 | |
| 戦後の新学制への外国史教育の導入 -新制高校社会科選択科目としての「東洋史」「西洋史」設置の意味- |
茨木 智志 |
| 昭和初期における東京女子高等師範学校附属小学校の作業主義歴史教育論 -飛松正の理論と実践を中心にして- |
福田 喜彦 |
| 《研究ノート》 | |
| 郷土サウンドスケープに関する地理教材の開発 -郷土「群馬県」の場合- |
山口 幸男 |
| フランス高校教育段階における「公民・法律・社会」科の理論と方法 | 大津 尚志 |
| 《研究の広場》 | |
| 小学校社会科教育における金融経済教育の基礎・基本 | 武部 浩和 |
| 民主主義を扱ったシチズンシップ教育の実践 -オーストラリア・ビクトリア州における中等教育学校の取り組み- |
大野 順子 |
| 《書評》 | |
| 梅津正美著『歴史教育内容改革研究-社会史教授の論理と展開-』 | 坂井 俊樹 |
| 社会認識教育学会編『社会認識教育の構造改革 -ニュー・パースペクティブ-にもとづく授業開発』 |
谷川 彰英 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第100号(2007年)
| 《第100号記念論文》 | |
| 日本社会科教育学会における社会化教育研究の「学」的樹立への動き -『社会科教育研究』創刊号から第20号までの掲載論文の分析を通して- |
戸田 善治 |
| 社会科教育学確立への努力 -第21号から第40号まで- |
野口 剛 |
| 社会科教育における「教育研究」の視座 -1970年代末~80年代の研究動向を概観して- |
熊田 禎介 |
| 戦後社会科教育研究の総括と新世代社会化教育研究への模索 -『社会科教育研究』第61号から80号までの掲載論文の分析を通して- |
谷口 和也 |
| 『社会科教育研究』には実践的研究が少なくはないか -21世紀の転換期社会科の中で- |
鎌田 和宏 |
| 《学会誌編集の軌跡》 | |
| 75年から89年まで学会誌編集に携わって | 影山 清四郎 |
| 学会誌の学術性向上を目指して | 篠原 昭雄 |
| 大判化への移行時代を振り返って | 市川 博 |
| 年間2号体制から3号体制への移行 | 西脇 保幸 |
| 学会誌編集事務に携わっての雑感 | 江口 勇治 |
| 《書評》 | |
| 永田忠道著『大正自由教育期における社会系教科授業改革の研究』 | 外池 智 |
| 《図書紹介》 | |
| 2006年度日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |