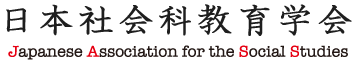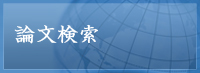機関誌目次
現在、検索できるのは「タイトル」「著者名」のみです。以下の手順で検索可能です。
- 右上の検索窓に「タイトル」「著者名」に含まれるキーワードを入力する。
- 「サイト内を検索」ボタンを押してから、検索を実行する。
No.1~10 | No.11~20 | No.21~30 | No.31~40 | No.41~50 | No.51~60 | No.61~70 | No.71~80 |
No.81~90 | No.91~100 | No.101~110 | No.111~120 | No.121~130 | No.131~140 | No.141~145
第131号-140号
第131号
| 特集 地域再生に向き合う社会科教育 | |
| 「地域再生」を担う人材育成をめざす社会科授業 ─ 学校と地域を結ぶしくみづくりからの提言 ─ |
竹内 裕一 |
| 地域学習は「地域再生」の基礎となりうるか ─ 青森県における教育現場での実践を通して考える ─ |
三浦 博英 篠塚 明彦 |
| 地域をともにつくる教育実践の現状と課題 ─ 小学校段階における社会認識形成と地域への関与をめぐって ─ |
前田 賢次 |
| 生活文化の価値を見直す地域学習の可能性 ─ 山陰の「一式飾り」を事例として ─ |
高橋 健司 |
| 福島の水産業の復興と社会科授業 ─ 福島の水産業をテーマにした社会科授業の構想 ─ |
白尾 裕志 |
| 多様な「意見表明」に価値を見い出す社会科授業の可能性と限界 ─「東日本大震災」と「水俣病事件」の授業を事例として─ |
古家 正暢 |
| 《調査研究》 | |
| 社会科教育の研究動向 ─ 2016年度の学会誌論文から ─ | 鎌田 公寿 |
| 中国における社会科教育の動向 ─ 小学校における「品徳と社会」から「道徳と法治」への変容を中心に ─ |
沈 暁敏 |
| 《研究論文》 | |
| 福島第一原発事故による自主避難をめぐる家族の葛藤を考える授業実践 ─ 原発事故、その時どうする?「留まる/避難する」家族会議 ─ |
前嶋 匠 |
| 《書評》 | |
| 吉永 潤著『社会科は「不確実性」で活性化する ─ 未来を開くコミュニケーション型授業の提案─』 |
栗原 久 |
| 藤原孝章著『グローバル教育の内容編成に関する研究 ─ グローバル・シティズンシップの育成をめざして─』 |
水山 光春 |
| 胤森裕暢著『「価値観形成学習」による「倫理」カリキュラム改革』 | 鈴木 隆弘 |
| 川口広美著『イギリス中等教育学校のシティズンシップ教育 ─ 実践カリキュラム研究の立場から ─』 |
坪田 益美 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第132号
| 特集 社会科における「評価」 | |
| 社会科における評価と学習指導の一体化 ─ 思考体制の変化と集団的思考をとらえる手がかりに着目して ─ |
溜池 善裕 |
| 「社会科の作文」の評価に関する実践的考察 ─ 中学校社会科歴史的分野「戦時下の人々」の指導を通して ─ |
倉橋 忠 |
| 哲学対話における「学習としての評価」の役割 ─ 高等専門学校「対話としての哲学・倫理入門」 「現代社会論」の実践分析を手がかりとして ─ |
得居 千照 |
| 《書評》 | |
| 鈴木哲雄著『社会科歴史教育論』 | 土屋 武志 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 | |
第133号
| 特集 社会科における「評価」 | |
| 授業コミュニケーションの分析をとおした社会科授業評価 ─ GTMA,会話分析,ポートフォリオ分析をとおして ─ |
小野間 正巳 |
| 《研究論文》 | |
| 戦後教育改革期の社会科における道徳的「学力」の測定・評価方法とその影響 ─ 国立教育研究所及び日本教育学会による学力調査の分析 ─ |
松本 和寿 |
| 《研究ノート》 | |
| 社会科における公害学習の焦点 ─ 水俣病学習の変遷を事例に ─ |
小川 輝光 |
| 初期中等社会科教育論構築の試み ─ 朝倉隆太郎『社会科教育法(一)(二)(三)』の場合 ─ |
相澤 善雄 |
| 《図書紹介》 | |
| 第67回日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |
第134号
| 特集 改めてグローバル化と社会科を考える | |
| グローバル化・反グローバル化時代におけるナショナルなものの取り扱い ─ 政治理論の社会科教育への含意 ─ |
蓮見 二郎 |
| 「グローバル社会の中の自分」をとらえる社会科教育 ─ コンゴの紛争資源問題を教材として ─ |
華井 和代 |
| 語用論的資質を育成する歴史授業 ─ 世界史単元「言説『貨幣』を考える」を事例にして ─ |
宮本 英征 |
| グローバル社会における多文化的社会科教育 | 桐谷 正信 |
| 草の根の人々の交流から考える日韓友好 ─ 旗田巍・浅川巧・藤本巧を中心に ─ |
高 吉嬉 |
| 小学校社会科はグローバル化にどう対応すべきか ─ イングランドの地理教育・空間論研究の成果を視点にして ─ |
佐藤 克士 |
| 探究学習における対話の原理 ─ グローバル時代における社会科教育研究方法論の提案を通して ─ |
田中 伸 Amber Strong Makaiau |
| 《調査研究》 | |
| 日本における社会科教育研究の動向(2017年度) | 鈴木 允 |
| アイデンティティの複数性と動態的な文化理解にもとづく議論に向けた関係構築 ─ 欧州評議会におけるシティズンシップ教育の事例を通して ─ |
橋崎 頼子 |
| 《研究論文》 | |
| 社会科歴史ディベートのジャッジと主権者教育 | 江間 史明 |
| 《書評》 | |
| 宮本英征著『世界史単元開発研究の研究方法論の探究 ─ 市民的資質育成の論理 ─』 |
佐藤 公 |
| 阪上弘彬著『ドイツ地理教育改革とESDの展開』 | 田部 俊充 |
| 川上具美著『思考する歴史教育への挑戦』 | 戸田 善治 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第135号
| 《研究論文》 | |
| 持続可能な水産業の在り方や消費者としての関わり方を考える社会科授業構成 ─ ESD の「統合的・協働的な解決アプローチ」に着目して ─ |
神野 幸隆 |
| 社会科パフォーマンス課題における真正性の類型化と段階性の実践的検証 | 豊嶌 啓司 柴田 康弘 |
| 問題解決学習を創出した社会科授業研究の論理と実際 ─ 愛知県新城市立新城小学校の授業研究システムを手がかりに ─ |
白井 克尚 |
| 《研究ノート》 | |
| シンガポール歴史教科書における史資料に基づいた探究課題 ─ GCE-Oレベルに基づく歴史教育の特色 ─ |
内藤 裕子 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 | |
第136号
| 《研究論文》 | |
| 社会科におけるゲーム教材の活用がその後の授業に与える学習効果 ─ ゲーム教材による「問題解決パースペクティブ」の形成に着目して ─ |
馬場 大樹 |
| 「政治的リテラシー」のラーニング・アウトカム評価とその実践的課題 ─ 論争問題の意見文をパフォーマンス評価し,その限界を鑑識眼的評価で補う評価方法 ─ |
岡田 泰孝 |
| 《書評》 | |
| 田尻信壹著『探究的世界史学習論研究 ―史資料を活用した歴史的思考力育成型授業の構築―』 |
篠塚 明彦 |
| 《図書紹介》 | |
| 第68回日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |
第137号
| 特集 社会科における文明の取り扱い | |
| 高等学校で教えられた世界史は欧米人の世界史だった | 安田 喜憲 |
| 「世界史」における文明の構図 ─ 21世紀の社会科学習の創造に向けて ─ |
田尻 信壹 |
| 社会科における「文明」の扱い ─ 太平洋の視点を導入する ─ |
中山 京子 |
| 「循環型文明社会」の構築をめざした小学校社会科授業モデルの開発と授業実践 ─ 小学校第3学年「スーパーマーケットのひみつ」を事例として ─ |
植田 真夕子 |
| 福澤諭吉の文明観に関する一考察 | 岩本 廣美 |
| 「暗記学習」の終焉 ─ 社会科歴史教育における「文明」の再検討 ― |
土屋 武志 |
| 韓国歴史教育における「近代文明」教育の新しい試み ― 「未来型近代文明」学習を中心とした「歴史」の内容構成 ― |
李 明熙 |
| 《調査研究》 | |
| 日本における社会科教育研究の動向(2018年度) | 日髙 智彦 |
| 米国の社会科教育研究の動向 ― Wiley Handbook of Social Studies Researchから見る ― |
福井 駿 |
| 《研究論文》 | |
| 「論証の構造」を活用した学習の授業構成 ― 同性婚を事例として ― |
小貫 篤 福澤 一吉 |
| 小選挙区選挙の過半数問題を教材にした中学校社会科授業の開発 ― 選挙制度批判学習の課題を克服するために ― |
藤瀬 泰司 |
| 《研究ノート》 | |
| 中国における学校の法教育 ― 「道徳と法治」教科書に着目して ― |
宮本 慧 |
| 権力を視点に時代を大観する社会科歴史学習 ― 大単元「権力で見る中世の日本」を事例として ― |
髙橋 壮臣 |
| 《研究の広場》 | |
| 社会科と家庭科が連携しての防災教育の深化 | 初澤 敏生 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第138号
| 特集 社会科における「思考力」の育成 | |
| 資料活用における批判的思考を育成する思考ツールの開発と評価 | 榊原 範久 杉山 立 大島 崇行 |
| 社会科教育における思考過程とICTの効果的な活用 ─ 中学校公民的分野の実践分析を通して ─ |
五十嵐 辰博 |
| 《研究論文》 | |
| 子どもを中心に据えた授業研究を通した教師の力量形成過程に関する研究 ─ 富山市立堀川小学校政二亮介のライフヒストリー的アプローチ ─ |
高橋 純一 坂井 誠亮 |
| 合意形成後の社会を体験させる「継続的社会構成学習」の提唱 ─ 「貿易ゲーム」のルール改変後の社会をプレイさせる授業を通じて ─ |
大山 正博 新 友一郎 |
| 《研究の広場》 | |
| 「国際バカロレア(IB)を視野に入れた社会科の実践と評価」について ─ 平成30年度春季研究会の報告 ─ |
野口 剛 志村 喬 田中 暁龍 |
| 《書評》 | |
| 佐長健司著『社会科教育の脱中心化 ―越境的アプローチによる学校教育研究―』 |
唐木 清志 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第139号
| 特集 社会科における「思考力」の育成 | |
| 社会科における「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法の開発 ─ 「振り返り場面」で生徒が立てた「問い」に着目して ─ |
大島 泰文 |
| 《研究論文》 | |
| 植民地期朝鮮の初等歴史教科書における「内鮮事歴」の内容検討 ─ 「原始・古代」を対象とする朝鮮総督府の意図と叙述の特色 ─ |
柳 準相 |
| 持続可能な社会の創り手に求められる批判的思考力の育成 ─ 小学校社会科第5学年「これからの食料生産」の実践をとおして ─ |
河野 晋也 |
| 社会系教員志望学生は社会科教育に関する講義の何にレリバンスを見出したか ─ 再生刺激法を通した教育大学大学生の自己報告を事例に ─ |
小栗 優貴 中山 智貴 |
| 《研究ノート》 | |
| 大学一年生がもつ政治意識の実証的な究明 ─ 計量的な分析手法を用いて ─ |
横山 奈緒子 |
| 教師が個人的な見解を表明することの教育的効果 ─ 政治的中立性に関する議論への一提言 ─ |
岩崎 圭祐 |
| 《研究の広場》 | |
| イギリスにおける歴史教育と教師教育 ─ A・キットソン氏を招いて:2019年国際交流セミナー報告 ─ |
二井 正浩 |
| 《書評》 | |
| 蒔田 純著『政治をいかに教えるか―知識と行動をつなぐ主権者教育―』 | 戸田 善治 |
| 荒井正剛著『地理授業づくり入門―中学校社会科での実践を基に―』 | 泉 貴久 |
| 渡部竜也著『Doing History:歴史で私たちに何ができるか?』 | 土屋 武志 |
| 《図書紹介》 | |
| 第69回日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |
第140号
| 《研究論文》 | |
| 「環境的正義」を中核とした社会科環境学習の構成原理 ─ ニュージーランドにおける初等社会科プログラムを手がかりとして ─ |
押井 那歩 |
| 地方自治体の農業政策を事例にした「政策評価授業」 ─ 政策的思考の育成を目指して ─ |
華井 裕隆 |
| アメリカ社会科における「インクルージョン」の授業方略 ─ T.Lintnerの「ビッグアイデア」を分析して ─ |
早瀬 博典 |
| 市民的資質としての問題提起力育成を目指した社会科授業設計 ─ 中学校社会科公民的分野小単元「エアコンの使用について考えよう」の場合 ─ |
横川 和成 |
| 小学校中学年社会科におけるメタ・ヒストリー学習の方略 ─ ドイツ事実教授教科書の分析から ─ |
服部 一秀 |
| 《研究ノート》 | |
| 「歴史的な見方・考え方」を深める協調学習の試みと展望 ─ 知識構成型ジグソー法を用いた文化史学習の実践 ─ |
渡邊 大地 |
| 《研究の広場》 | |
| 社会科におけるダイバーシティに関する授業実践等についての意識調査報告 ─ 学会員に対するアンケート調査を通して ─ |
2018~2019年度 ダイバーシティ委員会 |
| 《書評》 | |
| 李 明熙著『自己観点の歴史認識を育てる歴史学習の理論』 | 土屋 武志 |
| 太田 満著『小学校の多文化歴史教育─授業構成とカリキュラム開発』 | 川﨑 誠司 |
| 板橋孝幸著『近代日本郷土教育実践史研究 ─農村小学校教員による地域社会づくり構想の展開─』 |
伊藤 純郎 |
| 白井克尚著『戦後日本の郷土教育実践に関する歴史的研究 ─生活綴方とフィールド・ワークの結びつき』 |
溜池 善裕 |
| 渡部竜也著『主権者教育論 ─学校カリキュラム・学力・教師─』 | 栗原 久 |
| 佐藤浩樹著『小学校社会科カリキュラムの新構想 ─地理を基板とした小学校社会科カリキュラムの提案』 |
初澤 敏生 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |