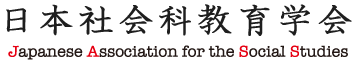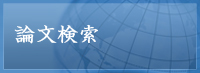機関誌目次
現在、検索できるのは「タイトル」「著者名」のみです。以下の手順で検索可能です。
- 右上の検索窓に「タイトル」「著者名」に含まれるキーワードを入力する。
- 「サイト内を検索」ボタンを押してから、検索を実行する。
No.1~10 | No.11~20 | No.21~30 | No.31~40 | No.41~50 | No.51~60 | No.61~70 | No.71~80 |
No.81~90 | No.91~100 | No.101~110 | No.111~120 | No.121~130 | No.131~140 | No.141~145
第101号-110号
第101号(2007年)
| 藤本光先生のご逝去を悼む | |
| I 特集 メディア教育とメディアリテラシーの育成-現実社会に向き合う社会科教育- | |
| 〈シンポジウム〉 | |
| シンポジウムの趣旨と概要 | 井門 正美 梅野 正信 |
| 高度情報化社会に向き合う社会科学習指導法 -メディアリテラシーの育成を視点にして- |
中村 哲 |
| 高度情報化社会における社会化教育の課題 -メディア・リテラシーと公民的資質- |
松本 康 |
| 主権者の育成を目指すNIE -現実の社会と人間に向き合う- |
佐藤 香 |
| 〈論考〉 | |
| NIEの今日的意義 | 影山 清四郎 |
| 社会科教育におけるメディアリテラシー像 -情報社会を主体的に構成する資質育成のために- |
佐藤 公 |
| II 研究調査 | |
| 社会科教育学における理論研究の動向 -2006年度の関係学会誌論文をもとに- |
永田 忠道 |
| 社会科教育における「実践研究」の動向 -2006年度の「公共性」にかかわる研究成果を中心として- |
竹澤 伸一 |
| モンゴル国における社会科教育の現状と課題 | 茨木 智志 |
第102号(2007年)
| ≪100号記念企画 社会科教育研究分析論文≫ | |
| 社会科教育における地域連携の動向と展望 | 松岡 尚敏 |
| 戦前期における歴史教育史研究の方法と課題 | 福田 喜彦 |
| ≪研究論文≫ | |
| 「机化」する子どもたちを起こす社会科教育の特質と教師の発達についての研究 -井ノ口貴史へのライフヒストリー的アプローチ- |
久保田 貢 |
| 教材選択の基準について -借上の図像をめぐって- |
加藤 公明 |
| 高等女学校における地理教育制度史の基礎研究 -他人相関的方法論の導入をめぐって- |
近藤 裕幸 |
| 学習者の素朴理論の転換をはかる社会科授業の構成について -「山小屋の缶ジュースはなぜ高い」- |
栗原 久 |
| ≪研究の広場≫ | |
| 2007年度 春季研究会(テーマ「小中高で国家をどう扱うか」)報告 | 研究推進委員会 |
| フランスにおける中等社会科系教科の教員養成 | 大津 尚志 |
| 日本の社会科の基本的文献や実践を中国語に訳して出版 | 市川 博 |
| ≪書評≫ | |
| 木村博一『日本社会科の成立理念とカリキュラム構造』 | 田中 武雄 |
| ≪図書紹介≫ |
第103号(2008年)
| 《研究論文》 | |
| 仕事認識の育成をめざす小学校産業学習の検討 -工業学習を事例として- |
大澤 克美 |
| 『ナショナル・カリキュラム地理』における学習テーマの変遷とイギリス地理教育論 | 志村 喬 |
| ≪研究ノート≫ | |
| 東アジア「歴史和解」と歴史共通教材 -最近の議論をもとに考える- |
坂井 俊樹 |
| ≪研究の広場≫ | |
| 日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」の近年の取り組みについて | 江口 勇治 |
| 国際地理オリンピックへの日本参加の意義 | 井田 仁康 |
| ≪書評≫ | |
| 二谷貞夫・和井田清司・釜田聡編『「上越教師の会」の研究』 | 田村 真広 |
| 加藤寿朗著『子どもの社会認識の発達と形成に関する実証的研究 -経済認識の変容を手がかりとして-』 | 江口 勇治 |
| 今野日出晴著『歴史学と歴史教育の構図』 | 伊藤 純郎 |
| 加藤公明著『考える日本史教育3-平和と民主社会の担い手を育てる歴史教育-』 | 野口 剛 |
| ≪図書紹介≫ | |
| 2007年度日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |
第104号(2008年)
| I 特集 改めて社会科教育の意義と可能性を探る-社会科にできること・できないこと- | |
| ≪シンポジウム≫ | |
| シンポジウムの趣旨とまとめ | 大友 秀明 谷本 美彦 |
| 社会科の可能性と限界-批判主義の立場から- | 池野 範男 |
| 社会科教育の意義と可能性 -政策レベルから、今後の在り方を探る- |
安野 功 |
| 社会科教育の意義と可能性 -小学校社会科ですべきこと、できること- |
長谷川 康男 |
| 愛国心教育と経済教育 -「社会科ですべきこと・すべきでないこと」の再検討- |
山根 栄次 |
| ≪論考≫ | |
| 改めて社会科教育の在り方を問う | 溝上 泰 |
| シティズンシップ教育における<社会科>教育の意義と可能性 | 臼井 嘉一 |
| II 研究調査 | |
| 社会科教育学における理論研究の動向 -2007年度の関係学会誌論文を手がかりとして- |
小瑶 史朗 |
| 社会科教育学における実践研究の動向 -2007年度の小学校社会科における研究成果について- |
鎌田 和宏 |
| カナダ ブリティッシュ・コロンビア州における環境学習の展開 -環境倫理を中心とした学習内容の転換- |
宮崎 沙織 |
第105号
| 《研究論文》 | |
| 社会的変容過程を動態的に捉える授業 -「外国人の医療保障問題」を事例として- | 三浦 朋子 |
| 《研究ノート》 | |
| 奈良県初期社会科におけるテスト問題に関する一考察 | 坂井 誠亮 |
| 《研究の広場》 | |
| 日本社会科教育学会国際シンポジウム報告 -東アジア社会科サミット- | 国際交流委員会 |
| 学習材としての社会科教科書の機能とその活用に関する調査研究 | 原田 智仁 |
| 《書評》 | |
| 伊藤純郎著『増補 郷土教育運動の研究』 | 外池 智 |
| 森茂岳雄、中山京子(編著) 『日系移民学習の理論と実践 -グローバル教育と多文化教育をつなぐ-』 |
原田 智仁 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第106号
| 《研究論文》 | |
| 政治的リテラシーを育成する社会科 -フェアトレードを事例とした環境シティズンシップの学習を通して- |
水山 光春 |
| 《研究ノート》 | |
| 安井俊夫の戦争平和学習論 | 鳥塚 義和 |
| 《研究の広場》 | |
| 今、なぜ「教職の専門性」なのか -課題研究「社会科教育の視点から見た教職の専門性」- |
戸田 善治 |
| アメリカ社会科研究会ミニシンポジウム 「アメリカ社会科におけるシティズンシップ教育の現状と課題」報告 |
藤井 大亮 桐谷 正信 |
| 《書評》 | |
| 安井俊夫著『戦争と平和の学び方 - 特攻隊からイラク戦争まで』 | 伊藤 純郎 |
| 田部俊光著『アメリカ地理教育成立史研究』 | 井田 仁康 |
| 《図書紹介》 | |
| 日本社会科教育学会著作権規定 | |
| 2008年度日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 中川浩一先生のご逝去を悼む | |
| 学会彙報 |
第107号
| I 特集 今、問われる社会科 -戦後社会科の総括と展望- | |
| 《シンポジウム》 | |
| シンポジウムの趣旨とまとめ | 坂井 俊樹 |
| 戦後社会科における世界史の教育 | 茨木 智志 |
| 社会科教育研究の総括と社会科教育史研究の展望 | 木村 博一 |
| 社会科授業研究の成果と課題 | 清水 毅四郎 |
| 社会科実践と子どもの社会認識 -「話し合う」こと、「書く」ことで深める社会認識- |
白尾 裕志 |
| 《論考》 | |
| 戦後歴史教育の課題・運動・実践の総括 -歴史教育者協議会の事例- |
宮原 武夫 |
| II 研究調査 | |
| 2008年の実践研究の動向 | 野口 剛 |
| 「地理的探求に基づく学習」に関する理論の展開 -米国・英国・豪州の研究動向の分析を中心に- |
金 玹辰 |
第108号
| 佐藤照雄先生のご逝去を悼む | |
| 《研究論文》 | |
| シチズンシップ「メディア単元」の事例研究 | 吉田 正生 |
| 自分と関わる発言・表現の多様化を図る社会科授業のPDCAサイクル -学習者が社会問題を認識し、自らの生き方を追究する授業(有田和正実践)分析- |
峯 明秀 |
| 昭和戦前期郷土教育におけるカリキュラム改造と村内教育体制構築の構想 | 板橋 孝幸 |
| 多元社会カナダにおける社会的結束に取り組むシティズンシップ教育 -アルバータ州社会科の「多様性の調整」に着目して- |
坪田 益美 |
| カリフォルニア州における環境リテラシー育成のための社会科プログラム -環境の原理に基づく学習内容の再構成に着目して- |
宮崎 沙織 |
| 《研究の広場》 | |
| 地域の何を、どのように、なぜ教えていくのか -日本社会科教育学会春季研究会「郷土愛は可能か?」の報告- |
渡部 竜也 |
| 「子どもの現実と社会科授業の成立」分科会での検討をめぐって | 木村 勝彦 |
| 《書評》 | |
| 中村和郎・髙橋伸夫・谷内達・犬井正編『地理教育講座 第Ⅰ巻~第Ⅳ巻』 | 戸井田 克己 |
第109号
| 《研究論文》 | |
| 現代フランスにおける国民国家相対化をめざした市民教育 -フランス中学校(コレージュ)「公民教育」教科書分析を中心に- |
宋 容九 |
| 社会科学習指導案の状況論的検討 -プランからの開放と状況への自由- |
佐長 健司 |
| ESDの視点を導入した地理教育の授業構成 -オーストラリアNSW州中等地理を事例として- |
永田 成文 |
| 《研究ノート》 | |
| 地域紛争学習に関する一考察 -高校地理歴史科・公民科における実践調査から- |
華井 和代 |
| 人権教育における人物学習の役割と課題 -ハンセン病訴訟判決文を用いた授業を事例として- |
福元 千鶴 |
| 専門高校における歴史を活用した探究型授業 -「天皇」「社会」を考えさせる活動をとおして- |
堀田 貴之 |
| 中学生の歴史意識の育成をめざす社会科授業の構想 -通史と地域史を関連付けたカリキュラムの作成と実践を通して- |
岡野 英輝 |
| 《書評》 | |
| 服部一秀著『現代ドイツ社会系教科課程改革研究-社会科の境界画定-』 | 大友 秀明 |
| 《図書紹介》 | |
| 2009年度日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 |
第110号
| I. 特集 社会科の教師力を問う -キャリア形成と実践の創造- | |
| 《シンポジウム》 | |
| シンポジウムの趣旨とまとめ | 馬居 政幸 |
| 社会科教員の授業力 -教育現場の現状と教職大学院の実践から- |
米田 豊 |
| 自律的な社会科授業実践の再構築 -指導法固定化の克服- |
小林 宏己 |
| 「話し合う」力を学力の一つと考える教師の育成 -あこがれの授業と優れた人物との出会い- |
市川 則文 |
| 香川県の学力向上施策と教師の授業力向上について | 大谷 伸一 |
| 《論考》 | |
| 非概念的「体験の海」としての博物館の意味 -歴史学習の知識論的読み解きによって- |
小笠原 喜康 |
| 社会科教員養成における地域の教育資源を活用した授業構成演習 -秋田大学教育文化学部社会科教育研究室の取り組みを事例として- |
外池 智 |
| カリキュラム・授業理論と教師教育論の連続的探求の必要性 -教科内容専門領域改革に向けた研究方法への提言:社会科を事例として- |
渡部 竜也 |
| 公共圏の変化における参加と提案の学習活動 | 大久保 正弘 |
| 博物館活用に求められる「教師力」 -「構成的な学び」の視点から- |
福山 文子 |
| II. 研究調査 | |
| 社会科教育学における理論研究の動向 -2009年度の関係学会を中心に- |
國分 麻里 |
| 2009年の社会科教育における実践研究の動向 | 荒井 正剛 |
| ドイツにおける地理教育カリキュラムと教育スタンダードの展開 -バーデン=ヴュルテンベルク州教育スタンダードを事例として- |
大高 皇 |