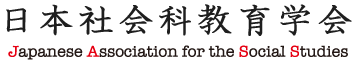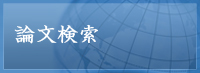機関誌目次
現在、検索できるのは「タイトル」「著者名」のみです。以下の手順で検索可能です。
- 右上の検索窓に「タイトル」「著者名」に含まれるキーワードを入力する。
- 「サイト内を検索」ボタンを押してから、検索を実行する。
No.1~10 | No.11~20 | No.21~30 | No.31~40 | No.41~50 | No.51~60 | No.61~70 | No.71~80 |
No.81~90 | No.91~100 | No.101~110 | No.111~120 | No.121~130 | No.131~140 | No.141~145
第111号-120号
第111号
| ≪研究論文≫ |
|
| 入門期社会科学習の新展開をめざして—「社会研究科」としての社会科の出発— |
片上 宗二 |
| 子どものライフヒストリーを創造する社会科教育—こどもエコクラブ卒業生の足跡調査を考察して— |
竹澤 伸一 |
| ドイツ中等歴史学習の構築主義的変革—ヘッセン州指導要領とゲゼルシャフツレーレ用教科書の分析をもとに— |
宇都宮 明子 |
| 昭和初期における成城小学校の歴史教育改革—内田庄次の理論と実践を通して— |
福田 喜彦 |
| 《書評》 |
|
| 志村喬著『現代イギリス地理教育の展開—「ナショナル・カリキュラム地理」改訂を起点とした考察—』 |
西脇 保幸 |
| 山口幸男著『地理思想と地理教育論』 |
村山 朝子 |
| 《図書紹介》 |
|
| 学会彙報 |
|
第112号
| 《研究論文》 |
|
| 世界史内容構成原理の比較研究—学習指導要領の再検討を通して— |
児玉 康弘 |
| 戦後補償問題に関する授業開発の研究—地域から世界を 過去から現在を考える— |
山元 研二 |
| 外交・安全保障政策の批判的検証を重視したドイツ平和教育の視座—社会科教科書における「コソヴォ紛争」の内容構成の分析を中心に— |
寺田 佳孝 |
| —文部省教科書局実験学校における社会科単元指導計画の作成—青木誠四郎の社会科教育論を手がかりに— |
篠﨑 正典 |
| 《研究ノート》 |
|
| 社会科における領土学習のあり方—北方領土を事例に考える— |
太田 満 |
| 《図書紹介》 |
|
| 第60回日本社会科教育学会全国研究大会報告 |
|
| 学会彙報 |
|
| 「社会科教育研究」編集規定 投稿要領 |
|
| 日本社会科教育学会著作権規定 |
|
第113号
| I. 特集 持続可能な社会の形成のために社会科は何ができるか |
|
| 《シンポジウム》 |
|
| 持続可能な社会の形成のための社会科・地理歴史科—高等学校地理歴史科における融合科目の提案— |
井田 仁康 |
| 地域多様性をふまえ持続可能な空間環境を実現する地理教育—イギリスにおけるESD地理教育から— |
志村 喬 |
| 持続可能な社会とこれからの歴史学習—現代の社会が「わかる」歴史学習に向けて— |
中尾 敏朗 |
| 社会科における認識の総合性と社会参加—持続可能な社会の形成と開発単元「フェアトレードと私たちのくらし」— |
藤原 孝章 |
| 持続可能な社会の形成のために小学校社会科ができること—「社会を見る3つの目」を育てる「市民」の学習の取り組みから— |
佐藤 孔美 |
| 《論考》 |
|
| シティズンシップ教育のための土木教育—「モビリティ・マネジメント教育」と「防災教育」の展開を— |
藤井 聡 |
| 「持続可能な社会」のための教育に向けて—ESD・開発教育の視点から— |
鈴木 隆弘 |
| 持続可能な社会の形成を目指した社会科教材開発の原理と方法 |
桑原 敏典 |
| ESDの源流をさぐる—環境教育と開発教育の視点から— |
上條 直美 |
| ESDと世界史教育—環境の視点が世界史に問いかけるもの— |
田尻 信壹 |
| II. 研究調査 |
|
| 社会科教育学における理論研究の動向—2010年度の学会誌論文等から— |
土屋 直人 |
| 社会科教育における実践研究の動向—2010年度の研究成果を中心にして— |
篠塚 明彦 |
| 韓国における社会科教育の動向—2010年の研究成果を中心に— |
真島 聖子 |
第114号
| 《実践研究論文》 |
|
| 小学校社会科における「情報単元」の改善とカリキュラム構想—英国シティズンシップのメディア単元をもとに— |
橋本 祥夫 |
| 高校生が法を通じて現代社会を主体的に考える授業—「法教育10年」の課題を踏まえて— |
渥美 利文 |
| メディアによる表面的な理解を問い直す小学校異文化理解学習—第6学年単元「メディアが伝えるオーストラリア」を事例に— |
松岡 靖 |
| 法とルールの基本的価値を扱う法教育授業研究—私的自治の原則の現代的修正を題材にして— |
中平 一義 |
| 「実践コミュニティ」の概念を導入した社会科の授業構成—予算編成ワークショップを事例として— |
関東 朋之 |
| 小学校社会科におけるモビリティ・マネジメント教育の可能性—交通渋滞を考える実践を通して— |
市川 武史 |
| 《研究論文》 |
|
| 「物語(り)」としての「伝統」—社会科地理学習における伝統の扱い方— |
伊藤 裕康 |
| 《研究ノート》 |
|
| 中学校社会科公民的分野における地域の町内会を活用した社会生活の問題解決—コンセンサス・ビルディングによる合意を中心として— |
堀内 和直 |
| 《書評》 |
|
| 二階堂敏惠著『現代アメリカ初等法関連教育授業構成論研究』 |
磯山 恭子 |
| 國分麻里著『植民地期朝鮮の歴史教育—「朝鮮事歴」の教授をめぐって』 |
茨木 智志 |
| 川﨑誠司著『多文化教育とハワイの異文化理解学習—「公正さ」はどう認識されるか』 |
山本 友和 |
| 山田秀和著『開かれた科学的社会認識形成をめざす歴史教育内容編成論の研究』 |
戸田 善治 |
| 田中 伸著『現代アメリカ社会科の展開と構造』 |
川﨑 誠司 |
| 田口紘子著『現代アメリカ初等歴史学習論研究—客観主義から構築主義への変革—』 |
桐谷 正信 |
| 伊藤純郎著『歴史学から歴史教育へ』 |
加藤 公明 |
| 《図書紹介》 |
|
| 学会彙報 |
|
第115号
| 《実践研究論文》 |
|
| 社会形成をめざす世界史の導入単元の開発研究 —単元「言説『帝国』を考える」を通して— |
宮本 英征 |
| 劇化活動を取り入れた歴史学習 —「牡丹社事件」の劇化を通して— |
曽田 祐太郎 |
| よりよい社会の形成に参画する資質や能力の基礎を培うことを目指した社会科学習の実際 —小学校第3学年小単元「地域の自慢、神田川」を手がかりに— |
齋藤 幸之介 |
| 高等学校公民科におけるシティズンシップ教育実践 —社会的課題解決の教育モデルに基づくさいたま市政策づくり授業— |
華井 裕隆
大久保 正弘 |
| 「地域生活の変貌と住民生活」の視点から持続可能な社会の形成を目指す公民科教育 —参加型学習教材「フードマイレージ買物ゲーム」を事例として— |
松井 克行 |
| 世界史における時事問題学習の意義 |
山本 勝治 |
| 《研究論文》 |
|
| 社会科授業における問いの状況論的検討 —正統的周辺参加としての学びを求めて— |
佐長 健司 |
| 《研究ノート》 |
|
| 相川日出雄の郷土教育実践を支えた考古学研究 —「考古学と郷土教育」を手がかりに— |
白井 克尚 |
教職大学院における教材開発と実践を活用した社会科教師の専門性 —裁判員制度の導入に対応した教科書教材開発を事例として— |
西村 公孝 |
| 《研究の広場》 |
|
| 東日本大震災・被災地の現在 —第61回全国研究大会(北海道教育大学札幌校)での報告— |
坂井 俊樹 |
| 《書評》 |
|
| 片上宗二著『"社会研究科"による社会科授業の革新 —社会科教育の現在,過去,未来—』 |
市川 博 |
| 宮本光雄著『社会科教育の本質に関する研究 —社会認識と公民的資質の関係性を中心に—』 |
工藤 文三 |
| 西尾 理著『学校における平和教育の思想と実践』 |
栗原 久 |
| 《図書紹介》 |
|
| 第61回日本社会科教育学会全国研究大会報告 |
|
| 学会彙報 |
|
第116号
| 梶哲夫先生のご逝去を悼む |
|
| I. 特集 これからの社会科教育のあり方を問う -多文化教育の実践的可能性- |
| 《シンポジウム》 |
|
| アイヌ民族に関わる学習(歴史・文化)から見えてきた多文化教育的視点 |
千葉 誠治 |
| アメリカにおける多文化教育の理論と実践 |
川﨑 誠司 |
| -公正な社会的判断力をどう育てるか- |
|
| マイノリティの子どもたちの組織化と保護者との連携 |
田渕 五十生 |
| -多文化教育の可能性をもとめて- |
|
| 社会科における多文化教育の再構築 |
中山 京子 |
| -ポストコロニアルの視点から先住民学習を考える- |
|
| 《論考》 |
|
日本における多文化教育の構築 |
松尾 知明 |
| -教育のユニバーサルデザインに向けて- |
|
| 多文化的性格の地域を教師はどのように教えるか |
草原 和博 |
| -社会科教師の意思決定の特質とその要件- |
|
| 共生と対話を志向する歴史授業構成 |
宮薗 衛 |
| -「日本の歴史」に埋め込まれた境界線を超えて- |
|
| アメリカの社会科における多文化的法教育の特色 |
磯山 恭子 |
| -社会正義の内容構成の分析を通じて- |
|
| II. 研究調査 |
|
| 国際化社会における社会科教育研究 |
小川 正人 |
| -米国社会科教育研究の動向をもとに- |
|
| 社会科教育における実践研究の動向(2011年度) |
大澤 克美 |
| -学習指導要領の改訂に着目して- |
|
| イギリスにおける歴史教育の動向 |
伊東 彩子 |
| -研究と実践から見出される展望と課題- |
|
| 学会彙報 |
|
第117号
| 《研究論文》 |
|
| 米国「国際教育」実践における NPO の役割 |
内山 知一 |
| -シアトル学区の教師・管理職を対象にした調査から- |
|
| 多民族学習としての小学校歴史学習 |
太田 満 |
| -アイヌ史の位置づけを中心に- |
|
| 《研究の広場》 |
|
持続可能な発展のための郷土学習の実践 |
松浦 賢一 |
| -北海道とフィンランドにおける共生の文化を視点に- |
|
| 《書評》 |
|
| 五十嵐誓著『社会科教師の職能発達に関する研究 -反省的授業研究法の開発-』 |
西村 公孝 |
| 竹中伸夫著『現代イギリス歴史教育内容編成論研究 -歴史実用主義の展開-』 |
野口 剛 |
| 和井田清司著『高校総合学習の研究 -自律的学習の展開-』 |
小松 伸之 |
| 桐谷正信著『アメリカにおける多文化的歴史カリキュラム』 |
梅津 正美 |
| 《図書紹介》 |
|
| 学会彙報 |
|
第118号
| 《研究論文》 |
|
| 観光研究の成果を組み込んだ「社会科観光」の授業開発とその評価 |
佐藤 克士 |
| -小学校第5学年 産業学習「観光産業」を題材にして- |
|
| 紛争解決への取り組みを学ぶ国際平和学習 |
華井 和代 |
| -リビア紛争に対する国際連合の取り組みを事例として- |
|
| 《研究ノート》 |
|
シンガポール小学校社会科教科書にみる人物の取り上げ方 |
吉田 剛 |
| -ナショナルシティズンシップ育成のために- |
|
| 《研究の広場》 |
|
研究推進委員会の活動の現状 |
研究推進委員会 |
| 東日本大震災への本学会の取り組み |
工藤 文三 |
| -大震災に向き合う取り組みの模索- |
江口 勇治 |
| 《書評》 |
|
| 土屋武志著『解釈型 歴史学習のすすめ -対話を重視した社会科歴史-』 |
二井 正浩 |
| 中山京子著『先住民学習とポストコロニアル人類学』 |
藤原 孝章 |
| 金 玹辰著『地理カリキュラムの国際比較研究 -地理的探究に基づく学習の視点から-』 |
志村 喬 |
| 加藤公明・和田悠編著『新しい歴史教育のパラダイムを拓く』 |
國分 麻里 |
| 《図書紹介》 |
|
| 第62回日本社会科教育学会全国研究大会報告 |
|
| 学会彙報 |
|
第119号
| 山口康助先生のご逝去を悼む |
|
| I.特集 リスク社会における社会科のあり方(存在意義)を考える |
|
| 《シンポジウム》 |
|
| リスク社会における社会科のあり方(存在意義)を考える |
木村 博一 |
| ―シンポジウムの趣旨とまとめ― |
|
| 「高リスク」社会の中で価値選択的課題にどのように向きあうか |
三石 初雄 |
| リスク社会の中の子ども像と学校,社会科 |
中妻 雅彦 |
| 子どもたちの歓声がこだまする福島の再生のために |
菅野 正寿 |
被災地・福島県の社会科教育に関する一考察 |
小田 賢二 |
| ―「正当にこわがる」意識を育むために― |
|
| 《論考》 |
|
社会科が担う防災意識の形成と減災社会の構築 |
寺本 潔 |
| 中等地理教育でリスク社会をどのように扱うのか |
吉水 裕也 |
| ―身近な地域の防犯環境設計を事例として― |
|
| 「リスク社会」研究の論理に基づく歴史学習改革の方向性 |
戸田 善治 |
| ―小・中学校における日本中世史学習を事例として― |
|
| リスク社会と社会科公民教育 |
藤原 孝章 |
| ―社会認識の課題と「社会に生きる」授業― |
|
| リスクテーキングなコミュニケーション能力の育成 |
吉永 潤 |
| ―N.ルーマンのコミュニケーション論とリスク論を踏まえた社会科教科目標の再検討― |
| II. 研究調査 |
|
| 社会科教育における防災教育研究の動向 |
三橋 浩志 |
| ―東日本大震災後の学会誌論文等を中心に― |
|
| 社会科教育における実践研究の動向(2012年度) |
岩野 清美 |
第120号
| 《質的研究論文》 |
|
| 社会科の授業記録における主観的な記述 |
中尾 敏朗 |
| ―質的研究としての授業研究の発展に向けて― |
|
| グローバルヒストリー教育におけるナショナルアイデンティティの扱いに関する質的研究 |
二井 正浩 |
| ―World History for Us All における単元 New Identities: Nationalism and Religion 1850-1914CE の実践を通して― |
| 《研究論文》 |
|
倫理的問題に対する価値観を形成する「倫理」の学習 |
胤森 裕暢 |
| ―ソクラテスとプラトンの「人物研究」を取り入れた民主主義の学習を事例に― |
| 中学校社会科における社会的構想力の育成をめざした単元開発と実践 |
鈴木 正行 |
| ―基底的価値としての「人間の尊厳」及び「人間の安全保障」に着目して― |
| 《研究ノート》 |
|
| 公民的資質を育成するための「社会貢献科」の創造 |
竹澤 伸一 |
| ―社会科教育の実践から理論への橋渡しを意図して― |
|
| 《研究の広場》 |
|
| フランスの歴史・地理科教員の「修士号要求」以降における養成・採用 |
大津 尚志 |
| 《書評》 |
|
| 藤瀬泰司著『中学校社会科の教育内容の開発と編成に関する研究―開かれた公共性の形式―』 |
服部 一秀 |
| 《図書紹介》 |
|
| 学会彙報 |
|
ページトップへ