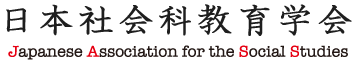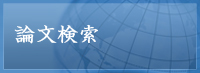機関誌目次
現在、検索できるのは「タイトル」「著者名」のみです。以下の手順で検索可能です。
- 右上の検索窓に「タイトル」「著者名」に含まれるキーワードを入力する。
- 「サイト内を検索」ボタンを押してから、検索を実行する。
No.1~10 | No.11~20 | No.21~30 | No.31~40 | No.41~50 | No.51~60 | No.61~70 | No.71~80 |
No.81~90 | No.91~100 | No.101~110 | No.111~120 | No.121~130 | No.131~140 | No.141~145
第61号-70号
第61号(1989年)
| 日米両国における国際化の進展と地理教育改革 | 中山 修一 |
| 社会科総合化への一試論―教科構造の問題を中心に― | 坂井 俊樹 |
| 連想語に見る「平和意識」の発達―「平和」と「戦争」の意味― | 松本 康 |
| 国際化の進展と国際理解教育 | 澁澤 文隆 |
第62号(1990年)
| “人権の世紀”における米国公民形成と社会科の性格―カリフォルニア州歴史 ―社会科学フレームワークの特色と背景を中心に― |
三浦 軍三 |
| 第一次教育令期における小学校の政治・経済的教育内容 | 木村 勝彦 |
| 地理的世界認識の発達と社会科カリキュラム | 山口 幸男 |
| 社会認識の教育原理の一つとしての再生的否定 | 桐田 克利 |
| 〈研究ノート〉 | |
| 文化交流圏としてのサハラ―新しい世界史学習の構想― | 原田 智仁 |
| 高等学校「現代社会」における国際理解教育 | 佐野 陽子 |
第63号(1990年)
| 〈特集 社会科教師の資質〉 | |
| 教師教育の教育課程における社会科専門性について―学生の履修の実態から― | 田中 史郎 |
| 開放制教師教育の理念と社会科教師の専門性に関する問題 ―私立大学教職課程の立場から― |
大森 正 松本 敏 |
| 〈研究ノート〉 | |
| サービス業の教材化に関する一考察―仮説単元「洗濯やさん」を通して― | 大澤 克美 |
| 社会認識の発展における連続と差異 ―小五と中三を対象とした授業分析による事例研究― |
広瀬 敏雄 |
第64号(1991年)
| 〈論稿〉 | |
| 社会科学習ソフトプログラムの理論的性格と活用課題 ―アメリカ社会科学習ソフトプログラムを事例にして― |
中村 哲 |
| 社会科地理教育における地域的視点 | 桜井 明久 |
| 〈研究ノート〉 | |
| 世界地誌学習における異文化理解の視点 | 西脇 保幸 |
| 社会科教師としての資質と授業づくりの力量 | 外山 英昭 |
| 意志決定能力を育成する「現代社会」の授業構成―ディベートによる討論技能の開発― | 猪瀬 武則 |
第65号(1991年)
| 〈論稿〉 | |
| Rugg, “Social Science Pamphlets”における社会科の本質 | 溝上 泰 |
| ラッグ社会科における「問題」の理解 | 江間 史郎 |
| 中学校社会科における総合的な社会認識を育成することの必要性とその論拠 | 小俣 盛男 |
| 〈研究ノート〉 | |
| 社会システムに関する子どもの認識の変容過程 ―築地学級における社会科討論の分析― |
吉永 潤 |
| 国際的視野に立った日本史教育の内容構成―日朝関係の取り扱いについて― | 土屋 武志 |
第66号(1992年)
| 〈論稿〉 | |
| 経済的社会化研究の成果と経済教育 | 栗原 久 |
| 木下竹次の「学習法」における「学習経済」 | 木村健一郎 |
| 柳田国男の郷土研究における「公民」の意義 ―戦後の社会科教育論への萌芽の観点から― |
溜池 善裕 |
| 〈研究ノート〉 | |
| 社会科における環境教育の重要性について―カモシカの被害を事例にして― | 関根 清 |
| 世界史教育における「文化圏」について | 宮崎 正勝 |
第67号(1992年)
| 〈研究論文〉 | |
| 社会の変化に対応できる社会認識内容及び方法―環境教材の検討― | 岩田 一彦 |
| 作業学習の違いによる学習効果の差異 ―アメリカ合衆国の農業地域の学習を例にして- |
中村 正巳 |
| 社会科における批判的思考育成の原理と方法 ―「議論」に基づく0' Relily の批判的思考育成原理― |
尾原 康光 |
| 〈研究ノート〉 | |
| シンガポールの児童の第二次世界大戦にかかわる対日イメージの形成 ―日本の児童との比較― |
井田 仁康 |
第68号(1993年)
| 〈研究論文〉 | |
| 社会科における「法教育」の重要性 ―アメリカ社会科における「法教育」の検討を通して― |
江口 勇治 |
| 「個人の集合体としての社会」という考え方の定着に果たした初期社会科の役割 | 佐藤 正幸 |
| 歴史授業改善への試み―言語表現の視点から― | 豊田憲一郎 |
| 社会科教育における消費者意思決定学習モデルに関する考察 | 南 景煕 |
| 〈研究ノート〉 | |
| ゲームの理論と方法を用いた国際理解の授業 ―「経済摩擦と国際協調」を事例として― |
新井 明 |
第69号(1993年)
| 〈特集テーマ:“新しい学力観”の検討と社会科教育〉 | |
| 社会科学力論と「知識」の位置づけ ―本多公栄氏の「社会科学力論」の検討を中心として― |
臼井 嘉一 |
| 「新しい学力観」の検討と社会科評価の在り方 | 宮本 光雄 |
| 社会科の学習意欲と実践批評の方法 | 村井 淳志 |
| 生涯学習における「自地域学」と社会科教育における地理分野 ―生涯を通して身につける学力とは何か― |
米地 文夫 |
| 〈研究論文〉 | |
| ハーバード社会科・社会的論争問題分析テストの学習評価論 ―問題場面テストによる社会科学習評価への示唆― |
棚橋 健治 |
第70号(1994年)
| 〈研究論文〉 | |
| 「新しい学力観」における「観点」の構造―その歴史的背景を中心に― | 谷川 彰英 |
| 経済的意思決定能力を育成する環境学習の授業構成 ―費用便益分析、限界分析の事例を中心に― |
猪瀬 武則 |
| 〈研究ノート〉 | |
| 「中等国史教科書編纂委員会」の歴史的研究 | 梅野 正信 |