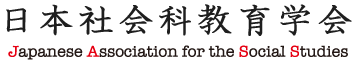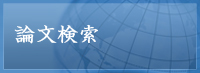機関誌目次
現在、検索できるのは「タイトル」「著者名」のみです。以下の手順で検索可能です。
- 右上の検索窓に「タイトル」「著者名」に含まれるキーワードを入力する。
- 「サイト内を検索」ボタンを押してから、検索を実行する。
No.1~10 | No.11~20 | No.21~30 | No.31~40 | No.41~50 | No.51~60 | No.61~70 | No.71~80 |
No.81~90 | No.91~100 | No.101~110 | No.111~120 | No.121~130 | No.131~140 | No.141~145
第141号-145号
第141号
| 《特集》社会科の実践者・研究者は子どもの学び、その成長をどのように捉えるのか? | |
| 小学校社会科における子供の学びと成長のとらえ ─ 学校教育及び授業実践者の立場からの分析と考察 ─ |
大矢 和憲 |
| 授業における生徒同士のコミュニケーションに見る社会科の学習過程 ─ 社会科教育への視座として ─ |
一柳 智紀 |
| 社会文化的アプローチは社会科教育研究を変えるか? ─ 米国社会科教育研究に押し寄せた質的研究革命を中心に ─ |
渡部 竜也 |
| 奈良女子大附属小の学習指導がどのようにそれを「しごと」にし子ども達を成長させていくか ─ 板書・日記・授業記録を5年間追って分かったこと ─ |
溜池 善裕 |
| 子どもの学びを促す社会科教師の「立ち止まり」の分析 ─ 「立ち止まり」を視点とした授業分析を通して ─ |
伊倉 剛 |
| 「学びに向かう力」を育成する世界の諸地域学習 ─ 中学校地理的分野「東南アジア」の授業実践を事例として ─ |
牛込 裕樹 |
| 子どもの学び,その成長をライフヒストリーからとらえる意味 ─ 社会科環境学習を共有した「こどもエコクラブ卒業生」の現在の「語り」から ─ |
竹澤 伸一 |
| 《研究動向》 | |
| 本における社会科教育研究の動向(2019年度) | 呂 光暁 |
| フランスにおける社会科系教科の教員養成と研究動向 ─ 歴史教育を中心に ─ |
大津 尚志 |
| 《研究論文》 | |
| アメリカ社会科におけるパワーを中核に据えた市民的関与の学習 ─ シカゴ学区公民科モデルカリキュラム“Participate”の分析を手がかりとして ─ |
久保園 梓 |
| 《研究ノート》 | |
| アジア・太平洋戦争に対する複眼的な歴史認識の育成 ─ シンガポールの歴史教科書における日本による占領に関する記述を題材として ─ |
小川 涼作 |
| 学会彙報 | |
第142号
| 《研究論文》 | |
| 科学技術社会論の成果を踏まえた社会的論争問題学習の開発研究 ─ トランス・サイエンスな問題を取り上げる小学校歴史学習の教育的意義 ─ |
吉川 修史 |
| 授業における教師の実践的知識の形成過程 ─ 長岡文雄「おかあさんのしごと」の授業実践記録の分析を通して ─ |
漆畑 俊晴 |
| 《図書紹介》 | |
| 第70回日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 | |
第143号
| 《追悼》佐島群巳先生のご逝去を悼む | |
| 《特集》「社会参画」の視点を生かすことで社会系教科の授業はどう変わるのか | |
| 社会参加学習における「振り返り」の重要性 | 峯 明秀 |
| 歴史教育における社会参加と社会参画 | 外池 智 |
| 社会参画の視点を生かして未来を共に創る社会科授業 | 真島 聖子 |
| システム思考に立脚した社会参画を見据えた「課題解決型の地理教育」の授業実践 | 泉 貴久 |
| 「社会参画」の視点を生かしたシティズンシップ教育とは | 林 大介 |
| 小学校での社会的論争問題学習における「判断の基準」の構築 | 佐藤 孔美 |
| 市民的変容の実存論的考察 | 田本 正一 |
| 特別支援教育における社会科授業に社会参画の視点をどう取り入れるか | 丹治 達義 |
| 《研究動向》 | |
| Engaging Social Studies Teacher Candidates in Civic Education and Social Justice Curriculum through Civic Engagement Projects in Social Studies Methods Coursework | Gayle Y. Thieman |
| 社会科の指導法に関する科目へ市民的関与プロジェクトを導入することを通して 社会科教師志望者を公民教育と社会正義のカリキュラムに関わらせること |
ゲイル・Y・シーマン (訳:唐木清志) |
| 日本における社会科教育研究の動向(2020年度) | 大髙 皇 |
| 《研究論文》 | |
| 現代社会理解をめざす中等教育歴史学習の授業構成 | 松井 昂 |
| 《実践研究論文》 | |
| リスク認知と自己効力感を高める授業は豪雨災害時の行動意図を変容させるか? | 望月 大 |
| 《実践研究ノート》 | |
| 熟議文化論の視点にもとづいた高校地歴公民科における宗教学習の再考 | 斉藤 雄次 |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第144号
| 《研究論文》 | |
| 民主主義政治を支える論争的問題の考察 ―欧州の動向を中心に― |
五十嵐 卓司 |
| 《研究ノート》 | |
| 外部人材の活用を通して社会的有用感の育成を目指す社会科授業構成 ―中学校社会科単元における外部人材に対する教師の働きかけに着目して― |
井上 昌善 |
| 《実践研究論文》 | |
| 「民主主義の担い手」となる市民を育成する方法としての紙上討論学習 ―同調圧力のもとで,討論を成立させるために― |
西村 太志 |
| 《書評》 | |
| 《図書紹介》 | |
| 学会彙報 |
第145号
| 《研究ノート》 | |
| 主権者教育において高校公民科教師が外部人材と連携するプロセスに関する研究 | 古野 香織 |
| 《実践研究論文》 | |
| 小学校における主権者教育プログラムの開発 ―模擬投票の「判断の規準」を話し合う「規準対話型」授業の分析― |
中 善則 |
| 時代の変化の捉え方が分かるパフォーマンス評価の開発と実践に関する研究 ―時代の構造的な理解を促すルーブリックの活用を通して― |
坂口 洋幸 |
| 《実践研究ノート》 | |
| 転売対策を題材とした経済分野の授業開発 ―効率性と公平性の両立を考える― |
橋本 想吾 前田 圭介 |
| 「歴史日記」の実践が生徒の歴史的思考力に及ぼす効果の事例的検証 | 細貝 采可 榊原 範久 杉山 立 |
| 《書評》 | |
| 《図書紹介》 | |
| 第71回日本社会科教育学会全国研究大会報告 | |
| 学会彙報 | |